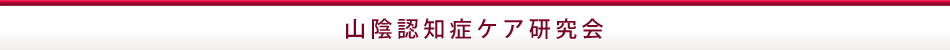開催記録
山陰認知症ケア研究会講師一覧(第10回~)
| 回数 | 開催日 | 演題 | 講師 |
|---|---|---|---|
| 第44回 | 令和7年4月19日(土) | 特別講演:『 抗Aβ抗体薬時代の認知症早期診断と地域連携 』 | かわさき記念病院 院長 長濱 康弘 先生 |
| 教育講演:『 大規模災害時に認知症の人を支えるために 』 | 東北医科薬科大学 老年・地域医療学 講師 石木 愛子 先生 | ||
| 第43回 | 令和6年11月4日(月) | 特別講演:『 認知症と嚥下障がいについて 』 | 医療法人ふらて会 西野病院 理事長・院長 西野 憲史 先生 |
| 教育講演:『 認知症の予防に向けたリハビリテーション 』 | 国立長寿医療研究センター リハビリテーション科部 リハビリテーション科医長 大沢 愛子 先生 | ||
| 第42回 | 令和6年4月7日(日) | 特別講演:『 認知症のトータルマネージメント 』 | 群馬大学大学院医学系研究科 脳神経内科学 教授 池田 佳生 先生 |
| 教育講演:『 遠隔音楽療法:基本形と応用例』 | 専修大学 ネットワーク情報学部 教授 小杉 尚子 先生 | ||
| 第41回 | 令和5年9月10日(土) | 特別講演:『 これからのアルツハイマー型認知症診断・治療 』 | 徳島大学大学院医歯薬学研究部 臨床神経科学分野 教授 和泉 唯信 先生 |
| 教育講演:『 認知症患者へのケアの基本 ~環境調整~』 | 島根大学医学部 地域・老年看護学講座 教授 原 祥子 先生 | ||
| 第40回 | 令和4年9月3日(土) | 特別講演:『 認知症の人の意思決定を支援するための方法について 』 | 京都府立医科大学大学院医学研究科 精神機能病態学 教授 成本 迅 先生 |
| 教育講演:『 認知症の人の健やかな口腔と食の支援 ~美味しく楽しく安全に~』 | 東京都健康長寿医療センター研究所 自立促進と精神保健研究チーム 認知症と精神保健 研究員 枝広 あや子 先生 | ||
| 第39回 | 令和4年5月28日(土) | 特別講演:『 言語の障害を主とする認知症 特に左側頭葉型アルツハイマー病、或いは晩発性意味認知症について 』 |
神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 教授 阪井 一雄 先生 |
| 教育講演:『 認知症ケアパスの作成と活用 ~ 当事者ニーズに基づく地域づくり ~ 』 | 東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム 研究部長 井藤 佳恵 先生 | ||
| 第38回 | 令和3年9月26日(日) | 特別講演:『認知症と歩行障害~フレイルと正常圧水頭症~』 | 山形大学医学部 内科学第三講座 神経学分野(脳神経内科) 教授 太田 康之 先生 |
| 教育講演:『認知症ケアパスの作成と活用 ~当事者ニーズに基づく地域づくり~』 | 国立長寿医療研究センター 企画戦略局 リサーチコーディネーター 進藤 由美 先生 | ||
| 第37回 | 令和3年5月15日(土) | 特別講演:『認知症予防:認知症リスクをどのように低減するか』 | 国立長寿医療研究センター・もの忘れセンター長 櫻井 孝 先生 |
| 教育講演:『認知症医療とケアで最近私が大切にしていることリフレクションと認知症看護 ~看護経験を実践に活用する~』 | 日本赤十字北海道看護大学看護学部 成人看護学(慢性) 教授 東 めぐみ 先生 | ||
| 第36回 | 令和2年9月27日(日) | 特別講演:『認知症カフェとは?今後期待される方向性』 | 社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター 研修部長 矢吹 知之先生 |
| 教育講演:『認知症医療とケアで最近私が大切にしていること』 | 東京慈恵会医科大学 精神医学講座 主任教授 繁田 雅弘 先生 | ||
| 第35回 | 令和元年9月28日(土) | 教育講演:『認知症に関する世界の潮流と実践研究の重要性~世界が注目する日本の知見とWHO 神戸センターの役割~』 | WHO 健康開発総合研究センター 医官 茅野 龍馬 先生 |
| 特別講演:『高齢者の不眠への対応』 | 医療法人社団更生会 草津病院 精神科 副院長 広島市西部認知症疾患医療センター長 岩崎 庸子 先生 |
||
| 第34回 | 平成31年4月7日(日) | 基調講演:『認知症高齢者の自動車運転』 | 慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室 教授 三村 將 先生 |
| シンポジウム:『認知症高齢者の自動車運転の課題解決に向けて』 | 演題1: 鳥取県警察本部運転免許課 髙村 太 氏 |
||
| 演題2: 自動車安全運転センター業務部長 岡本 努 氏 |
|||
| 演題3 NPO法人 高齢者安全運転支援研究会 理事長 越 和紀 氏 |
|||
| 第33回 | 平成30年7月14日(土) | 教育講演:『認知症の人と共に創る暮らし~“今”を生きる方々への関わり方~』 | (有)福祉ネットワーク・やえやま 代表取締役 當山 房子 先生 |
| 特別講演:『認知症ケアスタッフが知っておくべき脳画像』 | 日本医科大学大学院医学研究科 脳病態画像解析学講座 寄附講座教授 三品 雅洋 先生 |
||
| 第32回 | 平成30年3月17日(土) | 教育講演:『当事者に学び、共に築くまちづくり』~認知症ケアと地域ケア~ | 大牟田市認知症ライフサポート研究会 代表 社会福祉法人東翔会 グループホーム“ふぁみりえ”ホーム長 大谷 るみ子 先生 |
| 特別講演:『優しさという薬~八重子のハミングについて~』 | 佐々部 清 監督 | ||
| トークセッション 司会: 鳥取大学医学部保健学科 浦上 克哉 先生 |
グループホーム ホーム長 大谷 るみ子 先生 「八重子のハミング」 佐々部 清 監督 米子シネマクラブ 吉田 明広 会長 |
||
| 日本海新聞(2018年 3月20日掲載)に紹介されました 記事詳細 | |||
| 第31回 | 平成29年7月22日(土) | 『フレンドリーなコミュニティ~はたらくを通じて~』 | NPO町田市つながりの開 理事長 前田 隆行 先生 |
| 『認知症の人と家族に今できること』~レビー小体型認知症の早期診断と治療そして介護について~ | 大分大学医学部 総合診療・総合内科学講座 診療教授 吉岩 あおい 先生 | ||
| 第30回 | 平成29年3月19日(日) | 『若年性認知症の本人、家族へのサポート』 | 特定非営利活動法人認知症の人とみんなのサポートセンター 代表理事 沖田 裕子 先生 |
| 『認知症医療の最新知識』 | 一般社団法人日本認知症ケア学会 前理事長 本間 昭 先生 | ||
| 第29回 | 平成28年6月4日(土) | 『ボケてたまるか-認知症予防の対策を実体験して』 | 週刊朝日編集部 編集委員 山本 朋史 先生 |
| 『レビー小体型認知症の診断と治療-最新の知見もふくめて- 』 | 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 教授 スポーツ健康システム・マネジメント専攻長 水上 勝義 先生 | ||
| 第28回 | 平成28年1月31日(日) | 『認知症高齢者へのスピリチュアルケアとは』 | 社会医療法人栄光会栄光病院 チャプレン/グリーフカウンセラー 清田 直人 先生 |
資料 |
群馬大学大学院保健学研究科 リハビリテーション学講座 教授 山口 晴保 先生 | ||
| 第27回 | 平成27年7月4日(土) | 『認知症高齢者の権利擁護と虐待防止-支援者としてぶれないケアをしていくために-』 | 公益社団法人あい権利擁護支援ネット 代表理事 池田 惠利子 先生 |
| 『認知症の理解と対応-認知症の患者さんが見る世界-』 | 東京都立松沢病院 院長 齋藤 正彦 先生 | ||
| 第26回 | 平成26年11月24日(月・祝) | 『国際生活機能分類(ICF)の視点に基づく認知症ケア―生活障害の理解とケアに焦点をあてて―』 | 千葉大学大学院看護学研究科 地域看護学講座訪問看護学教育研究分野 教授 諏訪 さゆり 先生 |
| 『地域からの認知症施策の発信に向けて』 | 東京都健康長寿医療センター研究所 自立促進と介護予防研究チーム 研究部長 粟田 主一 先生 | ||
| 第25回 | 平成26年6月7日(土) | 『認知症、治せるの?』 | 大分大学医学部神経内科学講座 教授 松原 悦朗 先生 |
| 『認知症の原因疾患を踏まえた摂食・咀嚼・嚥下障害の特徴と食事支援』 | 北海道医療大学看護福祉学部看護学科地域保健看護学講座 教授 山田 律子 先生 | ||
| 第24回 | 平成25年12月8日(日) | 『精神科クリニックの医師として認知症にどう向き合うか~ケアスタッフとのより良い連携のために~』 | 医療法人和栄会 原田医院 精神科 副院長 原田 和佳 先生 |
| 『認知症の医療介護連携:統合エビデンスを目指して』 | 東北大学大学院医学系研究科 高齢者高次脳医学 教授 目黒 謙一 先生 | ||
| 第23回 | 平成25年6月8日(土) | 『被災地での認知症の取り組み~南三陸町にて~』 | 南三陸町地域包括支援センター 技術副参事 髙橋 晶子 先生 |
| 『東日本大震災における認知症と被災時のBPSD対策』 | 公益財団法人 舞子浜病院 名誉院長 田子 久夫 先生 | ||
| 第22回 | 平成25年1月27日(日) | 『パーソンセンタードケアと地域ケア ~認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるために~』 | グループホームふぁみりえ ホーム長 大谷 るみ子 先生 |
| 『認知症医療のエンドポイント』 | 国立長寿医療研究センター 院長 鳥羽 研二 先生 | ||
| 第21回 | 平成24年5月26日(土) | 『病院・クリニック・老健とGH等の現場から認知症を考える』 | 医療法人久幸会 今村病院 理事長 稲庭 千弥子 先生 |
| 『認知症ケア現状と課題』 | 日本認知症ケア学会 理事長 認知症介護研究・研修東京センター センター長 本間 昭 先生 | ||
| 第20回 | 平成23年11月29日(土) | 『認知症ケア課題解決「ひもときシート」の活用』 | 社会福祉法人 幸清会 理事長 大久保 幸積 先生 |
| 『認知症を抱えた方々を支えるために』 | 山口県立こころの医療センター 院長 兼行 浩史 先生 | ||
| 第19回 | 平成23年6月4日(土) | 『パーソン・センタードケアの理解と実践』 | いまいせ心療センター 副院長兼認知症センター長 水野 裕 先生 |
| 『介護負担および介護者支援マニュアル作成:認知症と自動車運転』 | 長寿医療センター研究所医療政策科学部 部長 荒井 由美子 先生 | ||
| 第18回 | 平成22年4月24日(土) | 『認知症ケアの本質と認知症ケアに対する指導のあり方 上級ケア専門士創設の意義とそのあり方』 | 大阪市立大学大学院 生活科学研究科障碍者・高齢福祉学研究室 准教授 岡田 進一 先生 |
| 『認知症の診断と治療:up date』 | 順天堂大学医学部精神医学講座 教授 新井平伊 先生 | ||
| 第17回 | 平成21年12月19日(土) | 「もの忘れフォーラム in yonago」 | |
| 第16回 | 平成21年5月16日(土) | 『認知症の人の心理的特徴とケアのあり方』 | 東北福祉大学 教授 認知症介護研究・研修仙台センター センター長 加藤 伸司 先生 |
| 『抗精神病薬の代わりに刺激療法』 | 秋田看護福祉大学 学長 佐々木 英忠 先生 | ||
| 第15回 | 平成20年12月13日(土) | 『認知症高齢者の終末期ケア ―日常生活援助を中心に―』 | 茨城県立医療大学保健医療学部 看護学科 教授 堀内 ふき 先生 |
| 『老年医学と高齢者医療の基本的な考え方』 | 東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座 東京大学医学部附属病院老年病科 教授 大内 尉義 先生 | ||
| 第14回 | 平成20年5月24日(土) | 『標準的な認知症ケアとは』 | 日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究科科長 教授 今井 幸充 先生 |
| 『認知症の医療とケア -私たちに今出来ること-』 | 認知症介護研究・研修東京センター長 聖マリアンナ医科大学 名誉教授 長谷川 和夫 先生 | ||
| 第13回 | 平成19年12月16日(日) | 『社会福祉国家デンマークが育んだ認知症ケアのセオリーと実践~一人ひとりの尊厳を支え、価値を高めるケア~ 』 | ロルフ・バング・オルセン氏 南デンマーク州立病院高齢者精神医療科長 ミアヤム・ゲーデ氏 南デンマーク州立病院精神看護師地域高齢者精神医療班認知症コーディネーター |
| 第12回 | 平成19年6月16日(土) | 『山口県周防大島町のもの忘れ健診システムについて』 | 山口県 健康福祉部 医務保険課 企画監 惠上 博文 先生 |
| 第11回 | 平成18年12月9日(土) | 『認知症の正しい理解』 | 愛媛大学大学院医学系研究科 脳とこころの医学 助教授 池田 学 先生 |
| 第10回 | 平成18年6月10日(土) | 『認知症とともに、認知症を超えて、誰もが安心して暮らせるまちづくり』 | 大牟田市グループホームふぁみりえホーム長 大谷 るみ子 先生 |